国際子ども権利センター 甲斐田万智子 編 荒牧重人 監修
こどもの権利条約について知りたくて、図書館で探して読んでみました。世界中で子どもが強制労働させられたり、食べられなかったり、差別されたりしていることは想像できました。ところが日本も決して子どもの権利条約から見ると優等生ではありません。こどもの権利条約に日本が批准したのが1994年だそうです。この本が書かれたのが2019年。日本にも多くの課題があることが書かれています。子どもたちの権利が守られていないと何度か勧告もいただいていることを知りました。
世間では国連で採択されたSDGsについて学校でも社会でも持続可能な社会を創ろうと声高に叫ばれています。その中でやはり子どもたちが安心で安全で活き活きと生活できる社会を創ることと重なることが多いようです。この本も子どもの権利条約とSDGsの17の目標を関連させて解説をしています。若すぎる少女が会ったこともない年配の男と結婚させられる、学校に行けず家族のためにカカオ農園で家族を食べさせるために働く子ども、国を追われて無国籍の子ども、内戦で戦う少年兵などなど大人たちの勝手で這い上がることが許されず犠牲になる子どもたち。
この本を読んでから調べてみると、何度も勧告を受けてきた日本ではようやく子ども家庭庁が発足して、ばらばらだった法律を一つにまとめてこども基本法がつくられ、年齢ではなく発達の観点から切れ目のない支援ができるようになったそうです。そして、こども大綱によって「こどもまんなか社会」に向けた取り組みがなされているそうです。しかし、今回の本を手に取るまで、子どもの権利や日本における子どもたちの状況についてあまり知らなかったのが申し訳なく感じます。
条約とは、国内法の最上位法である憲法の次に強制力のある法律だそうです。ところがそれが守られてこなかったというか‥‥日本における慣習が優先されてきたことに驚きます。そして、自分自身の子ども時代を考えながら、「当たり前」が本当は当たり前ではないことに気づかされます。では、自分の子どもにはどう接すればよいのかを改めて考えてしまいます。子どもは親とは違う一つの人格で子どもたちには固有の権利がある。そう頭でわかっていても普段の生活の中でその関係性を考えてしまいます。
改めて変えていくということが難しいことがわかります。それでも、子どもたちが活き活きとして、ウェルビーイングな状態でいられるような社会にしていかなければ、日本の国力はどんどん衰えていくことになります。
条約や法律という大きな枠組みだけではなく、自分の身近なところへ落とし込んでいくことをしていかなければ変わっていかないこともわかるし、行政任せや他人任せでは、絵空事になってしまいます。子どもたちを巻き込みながら?変な表現だなぁ子どもたちが当事者として社会にかかわれるような取り組みをしていく必要があるのだと改めて考えさせられました。


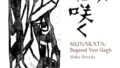
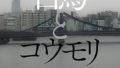
コメント