ファシリテーションを任されることになったので、改めて大切なことを確認してみようと思いで手に取った一冊である。
はじめに、でいきなり「教えることはしない方がいい」ということからスタートである。学ことに対する意識を変えることから始めないとファシリテーションは成り立たない。学ことは知ることと同義ではない。知っていることを深めていく、自分の中で有効活用する、新しい視点に気づく・・・そういう経験こそが学びだということなんだ。本書の中では@「学とは腑に落ちること」だとしている。知識獲得を目的とした教育ではなく、仲間と共に持てる知識位を共有しながら新たな発見や気づきを重視することが学ぶことであり、そんな学びの場を提供し、参加者がその場を活用できるような環境をいかにつくるかというところでファシリテーターが重要となってくる。
本書の流れでは、博報堂という大企業で勤めていた企業人が大学へ転職し大学で実際に学生とつくってきた経験と大切にしていることが書かれた本である。
まずは、ファシリテーションの本といえばパワポスライドがいくつか並んだような簡潔なHow to本がいくつかある中で、この本を選んだ理由は、文字がたくさんあったからである。読む中で著者の思いや、なぜそうするのかという説明、そしてその根拠となるデータや概念がそれぞれに載せられている。そいう背景をしっかりと書いた上で、実際の授業展開が書かれているので、読んでいる方としては状況が思い浮かべやすくとても参考になった。
そしてこの本の多くのページを割いて書かれているのは、学ぶ場の雰囲気づくりの方法だ。これができればあとは自然と流れはできると言わんばかりに、アイスブレイクからの話題の展開について書かれている。そして、その際に大切なことは頭で考えることの前に「感じること」なのだろうと読んでいて感じた。
読みながら、自分の行う学び場の中に足らない要素を確認しながら、取り入れた。なんとなく肉付けができたので、少しやる前に自信がついた。やっぱり一斉講義型の授業よりも、小グループの学び合いの方が有意義だと感じることができた。そして、ファシリテーションを行いやすくするための教具や物理的な場所の作り方も新たに知ることができたことも収穫となった。読みやすくわかりやすい内容で、この気づきを誰かに伝えたいと思わせる本だったなぁ。


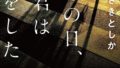

コメント